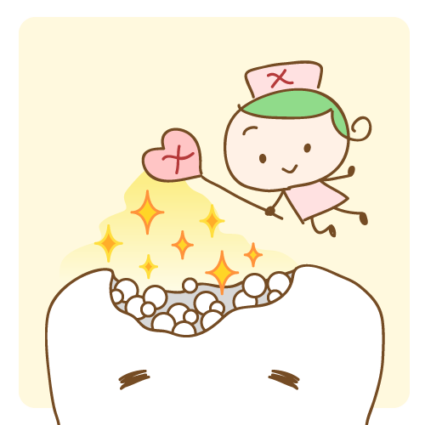こんにちは。仙台市若林区おろしまち歯科医院 臼井です。
前回に続いて「唾液」の持つ力についてのお話です。
唾液には、食べたものを分解する消化作用や、お口を潤す潤滑作用の他に、
1)殺菌・抗菌作用
2)自浄作用
3)再石灰化作用
4)緩衝作用
と、口や歯にとって、とてもありがたい働きがあることをお伝えしました。
それぞれがどの様な力であるのかというと、
1)殺菌・抗菌作用
リゾチームやペルオキシダーゼといった酵素の働きにより、口の中に入ってきた細菌が増殖することを防いでくれています。その様な働きのある物質が唾液中には10種類ほど含まれ、強い殺菌作用が発揮されています。
2)自浄作用
唾液は食事の時だけではなく、基本的に常に口の中に分泌され続けていて、口の中の汚れや細菌を洗い流してくれています。
3)再石灰化作用
唾液には、リン酸イオンやカルシウムイオンといったミネラルが豊富に含まれていて、これらは歯の主成分であるハイドロキシアパタイトの元で、酸によって失われた歯の成分が、唾液によって補充されて元に戻るということを常に繰り返しています。
4)緩衝作用
口の中は常に中性ではなくものを食べるたびに酸性に傾いています。歯はとても硬いですが酸には非常に弱く溶けてしまう性質があります。食べ物や飲み物に含まれる酸にさらされている時間が長いほど、また口の中が酸性になっている時間が長いほど歯はどんどん溶けてしまうことになります。唾液には酸性に傾いた口の中を中性に戻してくれる働きがあります。
食事をして酸性になった口の中が、唾液の働きによって中性に戻るには、30〜40分の時間が必要であると言われています。
食事をした後ですぐに歯磨きをするのは避けましょう。というのは、酸性になって歯が溶けやすい状態で歯磨きをすると歯を痛めてしまう恐れがあるからです。
食事でなくても何かを口に入れるたびに口の中は酸性になってしまうので、間食をした後も同じです。
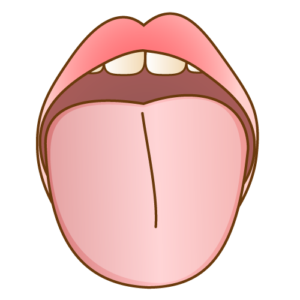
これらの唾液の作用を十分に活用するには、十分な量の唾液が口の中にある状態をなるべく長い時間保つことが大切です。
とはいえ、前回もお伝えしましたが、唾液は出そうと思って自由に出せるものではありませんし、お薬を飲んでいる方や、元々唾液の分泌量が少ない方も少なくありません、年齢とともに唾液の量が減少していくこともあります。
味覚が刺激されたり、食べるために口を動かすことで唾液の分泌は促されますが、再石灰化作用や緩衝作用を存分に活かすには、口にものが入っていない状態での唾液量が必要となります。
酸っぱいものや自分の好きな食べ物を想像したり、
キシリトール100%のガムを噛んだり、
頬や顎の下をマッサージしたり、
リラックスできる環境や時間を意識的に作ったり、
といったことを生活の中に取り入れて、食べている時以外にもお口の中を唾液で潤しておくことを心がけることで、むし歯だけでなく身体全体の健康に唾液の力を活かしてみましょう。