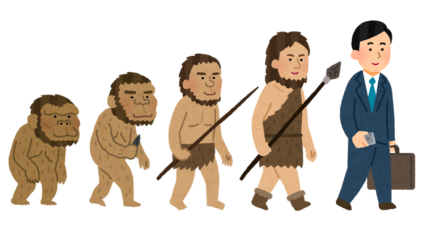こんにちは。仙台市若林区おろしまち歯科医院 臼井です。
前回は、歯は皮膚から進化したものであるというお話をしました。
途方もない長い年月をかけて皮膚から歯へと進化し、約4億3,000万年前に出現した棘魚類と呼ばれる古代の原始的な魚類が、顎骨上に物を噛むための歯をもつ最古の動物であると言われています。
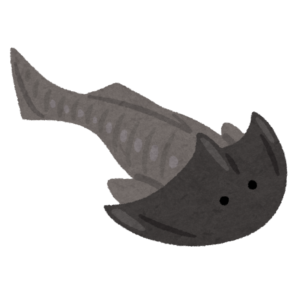
棘魚類は、その後絶滅してしまったそうですが、その後現れた軟骨魚類や硬骨魚類にしっかりと歯は受け継がれたようです。
一口に魚類と言ってもその種類は膨大で、食べるものも、プランクトンから他の魚、はたまたカニやエビ、貝などの非常に硬い物まで様々で、それぞれの食性に合わせて歯の形や数、噛む仕組みまで異なります。
それは、哺乳類でも同じ事で、草食動物のウマやウシでは、主に草をすり潰すための臼歯が発達していて、ライオンやイヌなど肉食動物は、噛み切るための牙(犬歯)など前歯がとても発達している事は想像しやすいですよね。
その中で、我々人類や類人猿など雑食性の動物は、前歯と臼歯がバランス良く並んでいると言えるかもしれません。
動物の歯は、何を食べるかによって、それぞれに合わせた最も効率的な形や数に進化しているのです。
ものを食べるための歯を獲得して以降、魚類→両生類→爬虫類→哺乳類と進化してきた中で、歯の質が大きく変わったのが、水中から陸上へと生活の場を移した時のようで、
水中生活をする魚類などの歯の表面を覆うのはエナメロイドという物質で、陸上生活をする爬虫類では我々と同じエナメル質であり、
その間にいる両生類では、水中生活をする幼生ではエナメロイドを、陸上生活となる成体ではエナメル質をもつものがいることが知られているそうです。
さらに爬虫類から哺乳類へと進化するさらに過程で大きく変わったのが、
①歯の形と数
爬虫類は、全ての歯が同じ形(多くは先の尖った円錐形)。
哺乳類は、切歯、犬歯、臼歯と位置によって形が異なります。
②歯の生え変わり
爬虫類は、一生の間に何度でも生え変わる多生歯性。(うらやましい)
哺乳類は、我々人類の様に一度だけ生え変わるニ生歯性、もしくは一度も生え変わらない一生歯性(ネズミなど)。
③そして歯の支持様式(歯がどの様に骨に支えられているか)
爬虫類は、歯と骨が直接くっくいている骨結合。歯と骨が一体化していて抜ける事は無く、折れたらまた生えてくる。
哺乳類は、骨に開いている穴(歯槽)に、歯が釘の様に刺さっている釘植(ていしょく)。歯と骨は分かれているため歯が抜ける事がある。乳歯以外では歯が抜けると二度と生えてこない。
という①〜③の3点です。
比べてみると、何度でも生えてきていたのに、抜けたら二度と生えてこなくなってしまったのは進化と言えるのか?と疑問になってしまいますが😅
細かいことはまたの機会にお話しますが、
シンプルで頑丈、使い捨てだった爬虫類の歯から、物凄く複雑な構造とハイスペックな機能を持つ代わりに、替えの効かない一生モノの歯へと大きく進化したと言えるのです☝️
と、ここまで哺乳類に進化してくるうちに、構造的にも機能的にも進化してきた歯なのですが、
サルから類人猿そして霊長類さらにヒトへと進化が進んでくると、少し様子が変わってきたようです。
簡単に言いますと、今の我々人類では、
歯の数が減り、顎や歯の大きさが小さくなってきている。つまり退化傾向にあると言われているのです。
原因はご想像の通り☝️
先にお話した様に、歯、顎は食べるものによって最適になる様に進化してきましたが、
自然のままの食物を口にする事が減り、元々歯や顎を使って行っていた細かくちぎったり、噛み砕いたりといった咀嚼の機能を、口に入れる前に道具や火を使って行うことが出来る様になった為と考えられています。
かといって、今の食生活を他の動物の様に変える訳にはいかないですよね😅
柔らかくて美味しいもの、柔らかいから美味しいものって沢山ありますし😁
ですが、教科書によると、この退化現象は自然に生じているものではなく、猿人以降の食生活による人類史的な現象である。ということなので、遠い未来の子孫達が元々歯のない人類に進化(退化)してしまうのを、仕方のない事だと考えるのも、何だか寂しい気がします。
小さい頃から、何でも小さく柔らかくして食べさせるのではなく、歯応えを楽しんだり、よく噛んで食べる事も食事の楽しみの一つとして覚えさせてあげる事も大切なのかもしれません☝️
生物が歯を使って食べることを始めて4億3,000万年。
人類が誕生して600万年。
人類が道具を使い始めて200万年。
さらにここ数千年の間に、人類が口にするものは格段に柔らかくて美味しくなってきたのでしょう。
美味しいものを美味しく食べられる喜びに、歯が必要無くなるという未来にはあまりなって欲しくないなぁ。と思います。
(参考)
三好作一郎 編著 後藤仁敏 小林寛 武田正子 花村肇 著 「簡明 歯の解剖学」 医歯薬出版株式会社,1996.