こんにちは。仙台市若林区おろしまち歯科医院 臼井です。
お口の機能には、
・食べること(捕食、咀嚼、食塊形成、嚥下)。
・話すこと(構音)。
・味わうこと(味覚、触覚)
など様々ありますが、
その中の味を感じる機能(味覚)は、主に舌に7,000〜10,000個存在する味蕾という器官に含まれる味細胞が、甘味、苦味、酸味などの味刺激に応答(反応)することで感じています。
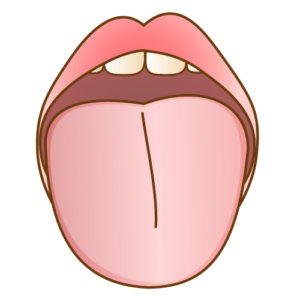
以前は、舌のそれぞれの部分ごとに感じることができる味が決まっていると考えられており、その分布を味覚地図と呼んでいましたが、今ではその考え方は誤りであったことがわかっています。
それぞれの味蕾が何かの味だけに反応するのではなく、全ての味蕾はどの味も感じることができているけれども、部位によって反応しやすい(感じやすい)味に差があるということなのだそうです。
時代ごとに根拠となる論文を元に正しいと思われていた考え方が、新たな研究や発見によって大きく変わったり否定されたりすることは、実は少なくありません。
その時、その時代の新たな考え方や、根拠に基づく正しい知識を常に更新していくことが、とても大切なんですね。
ところで、今回、唐突に味覚についての豆知識をお伝えしようと思ったきっかけは、
先日何気なく見ていた、お魚に詳しい「さかなクン」さんがウナギの謎を追うというテレビ番組で、
ウナギは全身に味蕾が存在しているため、全身で味を感じることができる。
ということに驚いたからでした。
そこで、ヒト以外の動物の味覚について調べてみると、
・ハエやチョウ、ガの仲間は一番前の足で味を感じることができる。
・イカやタコは吸盤で味を感じることができる。しかもタコの吸盤一つに200個以上、8本足全てで1,600万個の味覚受容器が存在する。(ヒトは約1万個)。
となんだかウナギ以上の驚きの事実が。
逆に、
・イヌの味蕾は1,700個、ネコは500〜800個程度とヒトと比べてもだいぶ少ないそうです。
味の感じ方は、動物の種によってこれほど大きく違うものなのだということを知り、改めて生物としてのヒトと他の動物との比較や進化の違いに興味が湧き、「動物のお医者さん」の影響もあって、北海道で獣医を目指していた若かりし頃を思い出しました。
これからも子どもたちの図鑑なども参考に、自分たちヒトの口や歯を通して、他の生き物の不思議や驚きの事実も紹介していくことがあると思います。
「へ〜」から自分のお口にも興味を持って頂けたら幸いです。
